エクスペリエンス エスティマ オプティマ マジストラ
10年ほど前、いやもっと前か、(今年、私と私のマックブックは卒業10年を迎えたばかりなので、みんなそれぞれ持っていた)、国内文化研究のナデシコとまではいかないまでも、少なくともほぼ同じ分野のStill On Something Nadezhdinaになろうと臆病にも夢見ていたとき、私はローマの詩に忘れられない印象を受けました。それがなかったら、私の人生のいろいろなことが違っていただろうと思うほど、忘れがたい印象です。
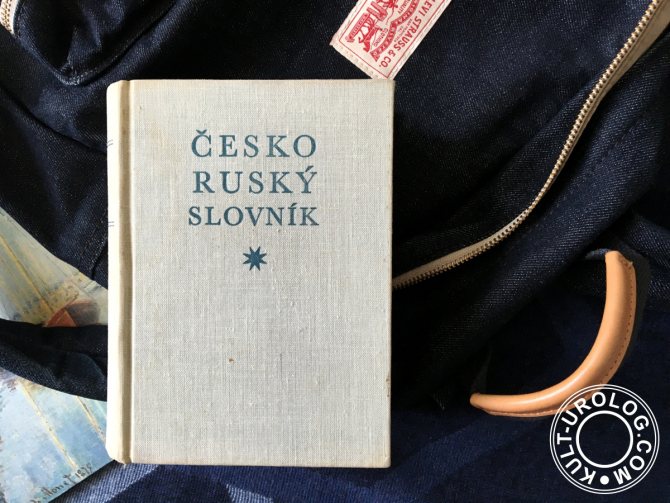
授業では、散文を読まされた。原始的な生活を送っていた裏切り者のガリア人のこと、すべてがローマに通じている道路で軍隊の前進に成功したが、イギリスへ行かなければならないので軍隊は反対方向へ行ったこと。もちろん、プロメテウスの肝臓をつつく鷲も。このような不朽の名作を音読してみると、いかに言葉が枯れているかがすぐにわかります。時折、明らかに誰かを呼び出そうとしているような感じ(ペンタグラムが曲がって描かれている悪趣味でチープな映画みたいな感じ)もあったが、全体の雰囲気は盛り上がらない。同時に、医学生に対するジョークも、単なるジョークでは済まなくなった。フランス文化がいかに身近なものであるか(つまり、ガリア人から遠く及ばなかったということ)を示すために、先生は詩を取り上げたが、それはワシとて良いものを得ることができなかったので、触れることは許されなかった。そして、その時にラテン語が鳴り始めたのです。あらゆる意味で。息を吹き返した。そして、それは美しかった。先生の方が経験豊富で、いろいろなものを読む時間があったのですから、当然です。でも、他の経験者はそんな風に読めなかったんです。そして、できるだけ長く使ってほしいという思いもありました。なるべく長く使ってほしいと思ったからです。ひとつには、このような演奏は他では行われていなかったからだ。それからは、ホラスが生きた人間のように思えてきた。もしかしたら、一度でも感情を味わったことがあるのかもしれない。しかも、違うものを。そして第二に、すべてのLorem Ipsumの後に、試験でみんなを待っているアナペスタスが何であるかという詳細な話が続いたからです。もちろん、誰も通らないようなやつ。しかし、その前に苦痛と屈辱を味わうことになる。だって、どうしようもないじゃないですか。いや、もちろん、先生は自分のテーマを愛している。そして、その気持ちを私たちにも伝えたいと思ったのでしょう。でも、怖がらせるのは彼の方が上手でした。
私がフランス語を学んだのは、まさにその響きに惹かれたからです(私たちの翻訳が怪しげな品質であること、したがって原典を調べたほうがよいことはすでに知っていましたが、それはフーコーのためというより、ジョー・ダッサンのためでした)。ボードレールの時もラテン語と同じぐらいでしたね。でも、それも美しくなって、自分でできるようになったので、身近な人にフランス語で何か言ってほしいと言わなくなりました。チェコのためにチェコ語を学び始めました。というのも、フランスの文化や歴史に触れた後(知れば知るほど困る)、言葉を知らなければ何もできないことに気づいたからです。表面的なイメージはつかめますが、本当に理解することはできません(少なくともそれに近いことは、現実的に考えてみてください)。このルールは、他のすべての文化にも当てはまります。そして、ゲルマニウムが好きな人は、パッケージに書かれている内容物も必ず読んでください。原語で。カマンベールではないチーズを生み出した文化に敬意を払え。
以前はチェコ語だからチェコ語が好きだったんです。音韻を整理した今、美しいので気に入っています。ふんわりとした優しい印象です。落ち着いていて、小康状態です。包み込むように、愛撫するように。チェコ語は愛の言葉だから、子音は適当なところでつまずくんだ。もちろん、最初はそのすべてが不気味に聞こえましたよ。ボヘミアングラスにフォークを刺すように。素材もそんな感じだったし、そうでもないんだけどね。というのも、音声認識ソフトの作者のすべてが、ある単語群から文章を作るだけでなく、その文章に意味を持たせることを課題としているからである。そこで読者は、明らかにクラスメイトとのコミュニケーションが負担になっている社会不適合者の学生として、普通の人が交わすようなフレーズではなく、授業中に彼女のアイテムを挙げ、チョークの色や壁やベンチの色に別々にこだわるという生きづらさを突きつけられるのである。読者に負担をかけないために、読者も暗記するように促しているのだ。言葉を発達させない。また、言葉の魅力を発揮するわけでもない。ラースカ "という言葉にはもっと大きな感動があるのに、なぜチョークを学ぶのですか?正しく、柔らかく発音する?あるいは、例えば「クルジェック」(kroužek)。今、一番好きな言葉です。すべてが美しいと思います。しかも、遠くまで行かなくても、最初にアルファベットをめくったときにすぐに見つかるのです。
そして、学生の生活の中に加藤ロムがいて、「人は詰め込むのではなく、読んで好きになるべきだ」と説明してくれると良いですね。そして、好きなものを全部読む。それよりも、自分で推測したほうがいい。現実との関係がまだ証明されていないテキストや、ケイト・ロームに気を取られることもない。そして、一般的に、チェコ語がロシア語にそれほど近くないという不思議な事情にも触れているのが注目される。確かに信じられないことですが、事実なのです。そうですね、チェコ語はロシア語に似ていますね。しかし、私が知っている他の言語と比べれば、それほどのことはありません。つまり、似ているところはあっても、やり過ぎる必要はないのです。また、ロシア語に慣れているよりも、フランス語の知識のほうが、未知との遭遇に役立つこともあります。そして、チェコには「未知なるもの」が十分にあるのです。
学校では、選択の余地はなかった。ジョンとジェーンが週末に友達の家に行ったことを月曜日までに知っていなければならないのなら、習うか習わないかの二択しかなかった。大学のラテン語は、創造性を発揮する余地がある。この見慣れた、しかし、もどかしく機能しないモデルを打ち破ったのは、フランス語の授業だけだった。とにかく チェコの台詞から、ほとんどすぐにモノローグに切り替わりました。難しかったけど、やりきりました。そして今、私はkroužekだけでなく、デンマークの王子の独白のお気に入りの翻訳も持っています。エリック・アドルフ・サデックによるものだ。ゲーテを長く研究し、1936年から1963年まで(つまり亡くなるまで)シェイクスピアの翻訳をした人。ボヘミアの翻訳と一緒で楽しいですよ。そして、もっと良いものがあると言われています。しかし、私はこちらの方が婉曲的だと思う。パステルナークの出番も少ないし。どうせ目の前のオリジナルでなければ、違いがあるはずですから。また、この写真から、エリック・アドルフは、私たちの先生が私たちを見ていたのと同じように、これからの世代を見ているのです。そして、そこは偶然ではなく、幼少期のトラウマだと思うのです。
関連出版物
シミュラクラ博物館
アーバンディケイ辞典 第二部 翻訳の難しさ
アートで綴る私の人生。第一部 クリエイティブ・アイデンティティの形成。起源と影響
アーバンディケイ辞典 第一部 仏蘭西語・民衆語・家庭語辞書
ラテン語のことわざと表現
А
A priori - もともと、あらかじめ。 最初から
.
Ab incunabulis - 揺りかごから。 ゆりかごから
.
Acta est fabula - パフォーマンスは終わった。
アド・ベスティアス、実行する。 獣に。
* i.e. Ad calendas graecas - 決して、木曜日の雨の後、雨が降ったときではなく、奴隷が殺されるとき、また捕虜のための時間が来たとき。
Ad calendas graecas - 決して、木曜日に雨が降った後ではありません。 グラシアスカレンダを追加。
. * ローマでは、カレンダーは毎月1日に支払われるものであった。ギリシャには暦がなかったから、この表現は「決して来ない時まで」という意味だった。
Alea jacta est - the lot is cast. * ジュリアス・シーザーの言葉です。紀元前44年、チサルピン・ガウル州のローマ軍団の司令官であったユリウス・カエサルは、単独での権力掌握を決意し、州の自然な境界となるルビコン川を軍隊とともに横断した。その際、総督はイタリア国外でのみ軍隊を指揮する権利を有するという法律を破り、ローマ元老院と戦争を始めた。
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt - 他人の悪徳は我々の目の前にあるが、自分の悪徳は背中の後ろにある。
Amat victoria curam - 勝利には仕事が必要です。
Ambitiosa non est fames - 飢えた者は自分の誇りを忘れない。 飢えはむなしいものではない
Amicus certus in re incerta cernitur - 困っているときの真の友。 忠実な友は不実な行為によって知られる。
Amicus Plato, sed magis amica veritas - プラトンは私の友人だが、真実はもっと大切だ。
Aqua et panis - vita canis - 水とパン - 犬の生活。* 16世紀の教皇シクストゥス5世が、「パンと水、そして祝福された生命」という有名な表現を変えたと言われています。
Amicus verus - rara avis - 忠実な友人 - 珍しい鳥。
Aquila non captatat muscas - 鷲は蝿を捕らえない。
Aquilam volare doces - 学者に教えることは、彼を甘やかすことにほかならない。 鷲に飛翔を教える
.
Arbor e fructu cognoscitur - 木はその果実によって知られる。
Ars longa, vita brevis、人生は短く、芸術は永続する。
Astra inclinant, non necessinant - 星は傾くが、強制はしない。
Audacia pro muro habetur - 勇気は壁に取って代わる。
Audentes fortuna juvat - 幸運は勇者を助ける。
Audiatur et altera pars - 反対側の声を聞かせる。* 論争を公平に聞くという表現は、アテネの宣誓書にある「私は告発者と被疑者を同じように聞きます」という言葉までさかのぼります。
Aurora musis amica - Aurora the muses friend, すなわち、朝の時間は科学と芸術の実践に最も適している。
Aut Caesar, aut nihil - シーザーか無かのどちらかです。
Aut vincere, aut mori - 勝つか死ぬか。
Ave, Caesar, morituri te salutant - こんにちは、シーザー、死に行く者たちはあなたに敬意を表します。* ローマの剣闘士が皇帝に挨拶したもの。
В
Barba crescit, caput nescit - 年とともに記憶は薄れていく。 ヒゲは伸びるが、頭は知らない。
Barba non facit philosophum - 髭は哲学者を作らない。
Bis ad eundem lapidem offendere - 同じ石に二度つまずくこと。
Bis dat, qui cito dat - 早く与える者は2回。
Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur - 良心的であることは、同じことを二度要求することを許さない。
С
Caecus non judicat de colore - 盲人は色を判断しない。
Cantilenam eandem canis - 同じ歌を歌いなさい。
Carpe diem(カルペ・ディエム)-今を大切にする。 今日をつかめ。
(エピキュリアのモットー)
Carthaginem delendam esse - カルタゴは滅ぼされなければならない(しつこいほどの念押し、執拗なまでの呼びかけ)。*この表現は、前184年の検閲官M.ポルキウス・カトーの言葉である。カトーが元老院で意見を述べるときはいつも、「それに、私はカルタゴは存在してはならないと考えている」と付け加えたという。
Cedant arma togae, concedat laurea laudi - 武器をトーガに、軍人のラウレアを市民の功績に譲りましょう。*キケロが『職務論』の中で引用した、失われた詩『執政について』の一節。この詩でキケロは、(謀反を起こしたカティリーナに)大勝利を収め、その市民的功績を称えた。
Circulus vitiosus - 膠着状態、悪循環。
Citius, altius, fortius - より速く、より高く、より強く!
Clavus clavo pellitur -くさびを打ち出すこと。
Cogito, ergo sum - 我思う、故に我あり。(ルネ・デカルト「哲学の素」)
Cognosce te ipsum - 汝自身を知れ。
Consensu gentium - 共通の同意による。 各国の同意による。
.
Consuetudo est altera natura - 習慣は第二の天性である。(キケロ「最高の善と最高の悪について」)


Contra fatum non datur argumentum(運命には逆らえない) - 運命には逆らえない。 運命に逆らうことはできない。
Contra jus - 法律に反する。
Contra rationem - 理性に反する。
Cornu copiae - 豊かな角。* 幼いゼウスをヤギの乳で育てたというアマルティアの神話に由来する。山羊は木の上で角を折り、アマルティアがそれを詰めてゼウスのもとに持っていきました。ゼウスは自分を養ってくれたヤギを星座に変え、その角を素晴らしい豊穣の角にして富の源としたのです。
Credo, quia absurdum est - 私は不条理だから信じる。
Cum tacent, clamant - 雄弁な沈黙。 黙っているときは、叫ぶ。
(キケロ「カティリーナに対する第一演説」) ※この演説は元老院の緊急会議で行われ、キケロは領事権限を超えて元老院にいるカティリーナに流罪を命じたものである。元老院議員たちは沈黙し、キケロはこの沈黙によって、ローマ市民を追放するには裁判所の命令が必要であるという法的手続き違反を認めたと結論づけた。
D
De gustibus et coloribus non est disputandum - 味覚と色彩は議論の対象にはならない。
De lingua stulta veniunt incommoda multa - 愚かな舌は多くの災いをもたらす。
Deliberandum est saepe, statuendum semel - よく議論し、一度決定する。
De minibus non curat praetor - 大ボスは些細なことは扱わない。
De mortuis aut bene, aut nihil - 死者については善か無かのどちらかである。
De te fabula narratur (mutato nomine) - その寓話はあなたについて語られている(名前だけが変更されている)。(ホラス、『風刺』)
デウス・エクス・マキナ(Deus ex machina)-上からの介入。 機械から出た神
. * 古代の悲劇に 神(機械仕掛けの装置、機械によって舞台に降りてくる役者)が突然介入し、その出現によって主人公たちの複雑な関係を解決する救いの技法である。それ以来、この表現は、困難な状況に対する予期せぬ解決策を意味するようになり、それはあたかも、より高い力の介入によって引き起こされたかのようである。
De visu - 外部から、視覚によって、具体的な対象との直接的な知見に基づいて、目撃者の目を通して。* 書誌や博物館のカタログなどでは、記載された対象物が編者によって個人的に調査されたことを意味します。
Dictum factum - 言ったことは実行される。
Dictum sapienti sat est - 賢者には十分な言葉です。
Dies diem docet - 日は日を教え、朝は朝を賢しとする。
Dies dolorem minuit - time heals. 日々は悲しみを和らげる。
Digitus dei est hic - これは神の指である。* 聖書(出エジプト記8章19節)には、ユダヤ人を故郷に帰すようエジプトのファラオを説得するために、神がエジプトに10の災いを与えたという話がある。4つ目は、ハエ。エジプトの祭司は、破壊的なハエを追い出そうとしたが、どうにもならなかった。祭司たちはパロに言った。"これは神の指だ "と。
Dixi et animam levavi - 言って、魂をほぐす。* 出典は聖書、エゼキエル書33章9節「もしあなたが悪人を戒めても、彼がその道から立ち直らないなら、彼はその咎の中で死ぬでしょう。
Docendo discimus - 教えることによって、私たちは自分自身を教えます。(セネカ「手紙」)
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt - 進む者は運命に導かれ、不本意な者は引きずられる。* ギリシャのストア学派の哲学者クレアントス(紀元前6世紀)の格言で、セネカがラテン語に訳した。
Dulce et decorum est pro patria mori - 祖国のために死ぬのは楽しく、名誉なことである。
Dum spiro, spero - 私が呼吸している間、私は願っています。
二人が喧嘩すると、三人目が喜ぶ。
Dura lex, sed lex - 法律は難しいが、それが法律である。
E
Edite, bibite, post mortem NULLa voluptas - 食べろ、飲め、死後の楽しみはない。* 古代の墓碑銘や食器によく見られるモチーフ。
Elephantum ex musca facis - ハエからゾウを作る。
Epistula non erubescit - 手紙は顔を赤らめることはない。(キケロ、親族への手紙)
Equi donati dentes non sunt inspiciendi, never look a gift horse in the mouth.
Errare humanum est - 人間には誤りを犯すことが内在している。
Est modus in rebus - すべてのものにはその尺度がある。 物事には尺度がある。
Et fabula partem veri habet - おとぎ話の中に真実がある。
Ex fontibus - first hand. 情報源から
Exercitium est mater studiorum - 運動は学習の母である。
Experientia est optima magistra - 実践は最良の教師である。
F
Fames - atrium magistra - 飢えは芸術の先生。
Feci, quod potui, faciant meliora potentes - 私はできる限りのことをした、できる者はもっとうまくやらせてくれ。* ローマ時代の領事が後継者に権力を譲る際に、成績表を締めくくるために用いた式を詩的に言い換えたもの。
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - 物事の原因を知ることができた者は幸せである。
Festina lente、何事もゆっくりやることです。 ゆっくり急ぐ。
Fiat lux - Let there be light! (聖書、創世記1:3)。
Finis coronat opus - 終わりは行為の戴冠である。
Fortuna caeca est - 運命は盲目である。* 幸運、幸福、運、繁栄を司るローマ神話の女神フォルトゥナは、両手に豊穣の角と操舵用のオールを持ち、空中に浮かぶ風船の上に立っていたり、翼を持ち、目隠しをした姿で描かれています。
Fortuna favet fatuis - 幸運は愚か者に味方する。
G
Gaudia principium nostri sunt doloris - 喜びは、しばしば悲しみの始まりである。
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - a drop chisel a stone instead by force, but by frequent falling.
H
Habent sua fata libelli - 本には自分の運命がある。
Haud semper erat fama(噂は常に間違いではない)。
Haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro - 本なしで学ぼうとする人は、ふるいで水を汲みます。
Historia est magistra vitae - 歴史は人生の教師である。(キケロ『雄弁家について』)
Hoc erat in fatis - そう、それは運命だったのだ。
Homo homini lupus est - man to man is a wolf. (プラウタス「ロバ」)
Homo proponit, sed deus disponit - 人間が仮定し、神が配置する。
Homo sine religione, sicut equus sine freno - 宗教のない人間は、手綱のない馬のようなものである。
Homo sum, humani nihil a me alienum puto - 私は人間であり、人間的なものは私にとって異質なものではないと考えています。
Honor habet onus - 言葉は重い。
Honores mutant mores, sed raro in meliores - 名誉は人物を変えるが、良い方向に変わることは稀である。
I
Ibi victoria, ubi concordia - 合意のあるところに勝利はある。
Ignorantia non est argumentum - 無知は議論にならない。
Ignoscas aliis multa, nihil tibi - 他人を大いに許し、自分は何も許さない。
Ignoti NULLa curatio morbi - 未知の病気を治すことはできない。
Ille dolet vere, qui sine teste dolet - 目撃者なしに心から悲しむ者。
In aqua scribere - 水の上に書くこと。
Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdam - あなたはスキュラに会い、チャリブディスを避けたいと願っています。
Innocens credit omni verbo - 誠実な人はすべての言葉を信じる。
In saecula saeculorum - いつまでも、いつまでも。
Inter arma tacent musae - 武器の中でミューズは沈黙している。
Inter caecos luscus rex - 盲人の間で、片目の王が。
In vino veritas(イン・ヴィノ・ヴェリタス)-真実はワインの中にある。
Ira odium generat, concordia nutrit amorem - 怒りは憎しみを生み、調和は愛を育む。
J
Judex est lex loquens - 裁判官は話す法律である。
Jus est ars boni et aequi - 法は善と正義の芸術である。
Justitia regnorum fundamentum - 正義は国家の基礎である。
L
Labor et patientia omnia vincunt - 忍耐と労働はすべてのものに打ち勝つ。
Lapsus calami - 見落とし。 ペンの滑り止め。
Lapsus linguae - 舌が滑ること。舌が滑る。
Legem brevem esse oportet - 法律は簡潔でなければならない。
Littera scripta manet - 書かれた文字が残る。
Lupus in fabula - easy as a wake. 寓話に登場する狼。
* このことわざは、「オオカミといえばすぐに現れる」という古代の信仰を反映しています。
Lupus non mordet lupum - オオカミはオオカミを噛まない。
Lupus pilum mutat, non mentem - オオカミは毛並みを変えるが、気性を変えることはない。
M
Magna pars sanitatis - velle sanari - 健康の大きな要素は、治りたいと思うことです。
Mala herba cito crescit - 悪い草はすぐに生えてくる。
Manus manum lavat - 手は手を洗う。
Margaritas ante porcos - (豚の前に真珠を投げること)。(マタイ7:6)。
Mea culpa, mea maxima culpa - 私のせい、私の最大の過ちです。* 11世紀以降のカトリックの宗教儀礼における、懺悔と告解のための式。
Medice, cura te ipsum - 医師よ、汝自身を癒したまえ。
Melius sero, quam nunquam - 遅いよりはましだ。
Mendacem memorem esse oportet - 嘘つきには記憶力が必要です。
Mendaci etiam vera dicendi nemo credit - 誰も嘘つきは信じない、たとえ真実を語る者でさえも。
Mendax in uno, mendax in omnibus(一つのことに嘘をつく者は、すべてに嘘をつく)。
Multum in parvo - 小さなことに多くのことを。
Ν
Nascuntur poetae, fiunt oratores - 詩人が生まれ、弁士になる。
Natura abhorret vacuum - 自然は空虚を忌み嫌う。
Nemo judex in propria causa - 誰も自分のことでは裁判官にはならない。
Nemo omnia potest scire - 誰もすべてを知ることはできない。
Nihil agenti dies est longus - 何もしない者には、一日は長い。
Nil sub sole novum - 太陽の下に新しいものはない。(聖書、伝道者の書1:9)
Noli tangere circulos meos(ノリ タンゲレ サークロス メオス):私の円に触れないでください。(アルキメデス)
Non est fumus absque igne - 火なくして煙なし。
Non olet - (お金が)臭くない。* ローマの歴史家スエトニウスは、ウェスパシアヌス帝がローマの公衆便所に税を課したとき、息子のティトゥスが不快感を示したと伝えています。ヴェスパシアヌスはティトゥスに新税の金を差し出し、「臭くないか」と尋ねた。ティテュスは「ノン・オレット」と認めた。
Non progredi est regredi - 進まないことは、後退することである。
Non rex est lex, sed lex est rex - 法は王の上にある。 王が法であるのではなく、法が王である。
Non scholae, sed vitae discimus - 私たちは学校のために学ぶのではなく、人生のために学ぶのです。
Novus rex, nova lex - 新しい王、新しい法、新しいほうきで掃除する。
NULLa calamitas sola - トラブルは決して一人では起こらない。
NULLa dies sine linea(ヌレア・ディス・シネ・リネア) - 線のない日はない。* 古代ギリシャの有名な画家アペレス(紀元前4世紀)は、「一本の線を引くことで、自分の芸術を実践しない日はなかった」と、プリニウスは報告しています。
NULLa regula sine exceptione - 例外なく規則を作らない。
NULLum malum sine aliquo bono - 何か良いことがなければ、悪いことはない。
O
Oderint, dum metuant - ヤツらが恐れている限り、憎ませればいい。*(カリギュラ皇帝の好きな言葉)
Oleum addere camino - 炉に油を足すこと。(ホラス、『風刺』)
Omne initium difficile est - すべての始まりは困難である。
Omnia mea mecum porto, I carry all mine with me. * キケロの『パラドックス』では、この言葉をギリシャの哲学者ビアントゥスの言葉としている。ペルシャ軍が彼の町を攻撃したとき、敵から逃れた住民は皆、自分の持ち物を持って町を出て行った。街を去るビアントは何も持っていかず、その理由を尋ねると「持ち物は全部持っていく」と答えた。
Omnia vincit amor, et nos cedamus amori - 愛はすべてに打ち勝つ、そして私たちは愛に服従する。(ヴァージル「回顧録」)
Omnis ars imitatio naturae est - すべての芸術は自然の模倣である。
Opus laudat artificem - 作品はマスターを褒め称える。
ああ、サンクタ・シンプリシタス! - O sancta simplicitas! * チェコの改革者ヤン・フスの言葉である。伝説によると、火あぶりにされたフスは、敬虔な動機から老婆が山盛りの柴を火に投げ入れたとき、この言葉を口にしたという。
O tempora! オー・モーレス! - オー・タイムス! モラルよ! (キケロ、カティリーヌに対する演説)
Otium cum dignitate(オティウム・キュム・ディグニテイト):尊厳のあるレジャー。* キケロの表現(「雄弁家について」)。このような余暇とは、科学、文学、芸術に捧げる余暇のことである。
Otium post negotium - ビジネスの後の休息。
P
Pacta sunt servanda - 契約は尊重されなければならない。
Panem et circenses! - パンとサーカスだ!* 帝政期のローマの暴徒の基本的な要求を表現した叫び。ローマ都市の平民は、政治的権利の喪失を受け入れ、無料のパン配布、現金配布、無料のサーカス興行で満足したのである。
Paupertas non est vitium - 貧困は悪徳ではない。
Per aspera ad astra - 茨を通り抜け星へ。
Per fas et nefas - 法と無法によって。
Periculum est in mora - 先延ばしにすることの危険性。
Per risum multum poteris cognoscere stultum - よく笑うことで、愚か者を見分けることができる。
ペルソナ・ノン・グラータ - 好ましくない人、信用されない人。* 外交において、公認された国の指導者の信頼を失い、罷免されなければならない官吏のこと。
Piscator piscatorem procul videt - 漁師は遠くから魚を見ている。
Plenus venter non studet libenter - 満腹は勉強にならない。 満腹になると、進んで学習しなくなる。
Pollice verso - 死刑宣告。 親指を下に向けた状態。
* 親指を下に向けた手は、ローマのサーカスで、敗れた剣闘士にとどめを刺すことを要求する条件付きのジェスチャーであった。
Post factum - 行為の後。
Post scriptum - 書かれたことの後(P.S.と略す)。
Primus inter pares(プリムス・インター・パレス) - 対等の中で最初に。
Procul ab oculis - procul ex mente - out of sight - out of mind; 心ならずも心ならずも。
Pro et contra -賛成と反対。
Pro forma - フォームのため。* ロシア語では「プロフォーマ」という単語が使われます - 形式を保つためにのみ何かをすること。
Q
Qualis dominus, talis servi、主人のように、しもべもまた然り。
Qualis rex, talis grex - 王のように、社会もまた然り。
Qualis vir, talis oratio - 人である以上、言葉もまた然り。
Qui fuit rana, nunc est rex - 汚物から威厳へ。 カエルだった者が、今は王様になった。
Qui quaerit, reperit - 探す者は見つける。
Qui seminat mala, metet mala - 悪を蒔く者は悪を刈り取る。
Quisque fortunae suae faber - 各々が自分の幸福を作るのです。
Quod erat demonstrandum - 証明されなければならなかったもの(略称:Q.E.D.)。
Quod in corde sobrii, id in lingua ebrii - しらふの人が心に抱くことを、酔っぱらいはその舌に抱くのです。
Quod licet Jovi, non licet bovi - ジュピターに許されることは、雄牛に許されない。
Quot homines, tot sententiae - 意見の数だけ人がいる。
Quot servi, tot hostes - 奴隷の数だけ、敵も多い。
R
その事柄を極めれば、言葉は後からついてくる。
Repetitio est mater studiorum - 反復は学習の母である。
Res publica est res populi - 共和国は人民の仕事である。
Risus sardonicus - 無愛想な笑い。* サルデーニャ島に生育する毒草、サルドニカ・ヘルバによる中毒が原因で、顔の痙攣に似た苦笑いをすると古代人は言っている。
S
Saepe stilum vertas - もっと頻繁に改訂し、文章を丁寧に書きましょう。 ペンを回す回数を増やす。
* ホラス「風刺」)スティルスは、ギリシャやローマで蝋引きした板に文字を書くのに使われた棒の名前です。一端が尖っており、蝋に引っ掻いて文字を書くのに使用された。反対側にはヘラのような形をしていて、これは蝋を滑らかにするために使われる。文字を修正するには、書かれたものを消して、スタイルを回して蝋を滑らかにする必要がありました。
Salus populi summa lex est - 人民の善は最高の法である。
Scio me nihil scire - 私は自分が何も知らないことを知っている。
Sero venientibus ossa - late comers (get) the dice.
Sic transit gloria mundi - そう、この世の栄光は過ぎ去る。* 将来のローマ法王が叙任される際、地上権力の亡霊の証として、目の前で布を燃やしながら語りかける言葉。
Sine ira et studio - 怒りや偏見を持たずに。* ローマの作家コルネリウス・タキトゥスは、歴史家の義務として、怒りや偏見を持たずに物語ることを書いています。
Si tacuisses, philosophum mansisses - もしあなたが黙っていたとしても、あなたは哲学者のままでしょう。
Sit mens sana in corpore sano - 健康な身体には健康な精神がある。
Si vis amari, ama - 愛されたいなら、愛せ。
Si vis pacem, para bellum -平和を望むなら、戦争に備えよ。
Si vox est, canta(シ・ボックス・エスト、カンタ) - 声があるなら歌いなさい。
Sub rosa - こっそり、ひそかに。 サブローザ
* 古代ローマでは、薔薇は秘密の象徴とされていました。宴席のテーブルの上に薔薇の花を飾ると、客はその席での会話はすべて秘密にしなければならないことを知ることができた。薔薇はヴィーナスと沈黙の神ハルポクラテスの花であり、愛の喜びを秘密にすることを見守ったことから、沈黙のシンボルとなったのである。
Suum cuique - 人それぞれです。
T
Tabula rasa - きれいな場所。 スクラブ入りのボード。
Tempora mutantur et nos mutamur in illis - 時代は変わり、我々はそれとともに変化する。
Terra incognita - 未知の土地。* 古代の地形図には、地球の未踏の地を表す言葉として使われていました。比喩的な意味で、まったく未知のものという意味です。
Tertium non datur、3番目は与えられない。
Timeo Danaos et dona ferentes - 私はダナイ人と贈り物を持ってくる者を恐れている。(ヴァージル『アエネイス』)
Tres faciunt collegium - 3人は共同体を構成する。
U
Ubi societas, ibi jus - 社会があるところには法律がある。
アルティマ・レシオ - 最後の議論、最後の手段。
Una hirundo non facit ver - 一羽の燕は春を作らない。
Urbi et orbi(ウルビ・エト・オルビ)-都市と世界へ。* この言葉は、13~14世紀にローマと全世界のカトリック教会の長として新たに選出された教皇を祝福するために受け入れられた公式の一部であり、全世界に教皇を祝福する公式となったものである。
Ut salutas, ita salutaberis - あなたが挨拶するように、あなたも挨拶されるのです。
V
Vade in pace(ヴァデ・イン・ペース)-平和に行こう。* カトリックの司祭が告解の後、赦免の際に話す言葉。
Vademecum - ガイドブックや参考書などの通称。 一緒に来てください。
Vae victis - 敗北者に災いあれ。* 390年のガリア人との戦争で、ローマは敗れ、1000ポンドの金を支払うことになった。恥ずべき取引に加え、屈辱もあった。ガリア人が持ってきた秤は間違っており、ローマ人がこれに異議を唱え始めると、あるガリア人が秤にさらに剣を突き立ててこう言ったのだ。「災い転じて福となす そして、ローマ人はそれを我慢していたのです。
Vale et plaudite(ヴァレ・エ・プラウディット) - 別れの挨拶と拍手。* ローマ演劇で、上演終了時に俳優が舞台から語る最後のフレーズ。
Vanitas vanitatum et omnia vanitas - 虚栄の虚栄、すべての虚栄。(聖書、伝道者の書1:2)
Veni, vidi, vici - 来た、見た、征服した。* プルタークによれば、ユリウス・カエサルはこのフレーズで迅速かつ輝かしい勝利を報告した。
Verbum manet, exemplum trahit - 言葉は興奮させ、例は魅惑する。
Veritas odium parit - 真実は憎しみを生み、真実は目を刺す。
Videant consules, (ne quid res publica detrimenti capiat) - 領事たちに、共和国が損害を被らないように見守ってもらいましょう。*元老院の非常事態令で、領事に独裁権を与えた非常事態の宣言を意味する。
Vim vi repellere licet - 暴力は力によって撃退することが許される。
Vis inertiae - 惰性の力、保守性。
Vita sine libertate nihil est - 自由なき生命は無である。
Vivere est cogitare - 生きることは考えること。(ヴォルテールのモットー)
Vivos voco, mortius plango, fulgura frango - 私は生者を呼び、死者を悼み、雷を打ち砕く。* シラーが詩「鐘の歌」の碑文として使用した、ヨーロッパ最古の修道院の鐘の碑文。
Volens nolens - willy-nilly. 喜んで、不本意ながら。
Vox clamantis in deserto - 荒野で叫ぶ者の声。(ヨハネ1:23、マタイ3:3、ルカ3:4、マルコ1:3)。
Vox populi - vox dei - 民衆の声は神の声である。
